1級建築士・2級建築士の受験資格。通信制大学・通信講座。
建築士になるための実務経験とは?
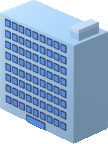
日本の建築士の資格は、一級、二級、木造の3種類があり、いずれも国家試験に合格した後、資格者名簿への登録を受け、免許の交付を受けることで業務ができるようになります。
ただし、建築士試験は誰でも受けられるものではなく、受験資格を満たしたもののみが受験することができます。
資格要件には大きく学歴要件と実務経験要件の2種類があり、最終学歴に応じて必要となる実務経験の期間が異なります。
建築士受験資格の実務経験とは?
ここでいう実務経験とは、建築物の設計や工事監理をするために必要な知識や技能を身につけられる業務のことです。
これに該当しない業務は、どんなに建築に関係するものであったとしても経験した期間に含めることはできません。
二級と木造の建築士試験では、大学、短大、高専のいずれかで国土交通大臣が指定した科目を履修した上で卒業した人と、建築設備士の資格を持っている人は、実務を全く経験していなくても受験することができます。
しかし、高校および中等教育学校(中高一貫校)を卒業した人だと学校を出てから3年以上、建築に関係する学歴が無い人だと7年以上の実務経験が必要となります。
最終学歴によって異なる年数
一方、ほぼすべての建築物の設計や工事監理業務に従事できるようになる1級建築士の国家試験では、より細かく実務経験要件が定められています。
大学で大臣指定の科目を履修して卒業した場合であっても、少なくとも2年は実務を経験していなければなりません。
また、3年制短大の卒業者は最低3年、2年制短大および高専の卒業者だと最低4年の実務経験が必要となっています。
また、2級建築士の免許取得を経て1級の試験に挑戦する場合は、2級建築士の資格登録が行われた日から、少なくとも4年間の実務の経験を積まなければなりません。
もし、建築に関係する学歴がない状態から1級建築士を目指すのであれば、建築設計事務所などに入って、7年間で設計や工事監理について勉強して二級の国家試験を受け合格後、さらに実務を4年間経験すれば、一級の国家試験を受ける所までたどり着くことができます。
しかし、大学で建築関係の学科を専攻し、国土交通大臣指定の科目の単位を取得して卒業した人は、たった2年の実務の経験だけで、2級建築士の国家試験をスキップして、いきなり1級の試験を受けることができます。
社会人になってから建築設計の世界に興味を持つと、2級の免許証の交付手続きの期間も考慮に入れると、少なくとも12年は修行をしなければなりません。
卒業生の体験談多数、自分に合った大学選びの参考にしてください。