1級建築士・2級建築士の受験資格。通信制大学・通信講座。
建築士と設計士の違いとは?
注文住宅を建てるときに、必ず相談するのが設計を担当する専門家です。
専門家と繰り返し打ち合わせをしながら、頭にイメージする理想を形にしていきます。
しかし、家づくりを進めていると、設計を担当する専門家には、建築士と設計士の2種類あることに気付くでしょう。
どちらも建築物の設計をする専門家なので、一般的には同じと思われがちですが、この2種類にはそれぞれ違いがあります。
建築士
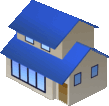
建築士には一級や二級などの国家資格があり、国によって認められている人です。
法律で様々な業務を行うことが認められており、建物の設計だけでなく工事現場の管理や依頼人に変わって行政手続きを代理で行ったり、不動産の鑑定評価や指導監督なども行うことができます。
設計を担当する建築物についても、面積などに特に制限はありません。
一般的な住宅からマンション、さらにはビルなどの建築物の設計に携わることもができます。
設計士
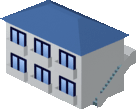
それに対して設計士には、国が認める国家資格はありません。
法律では、100平方メートル未満の木造住宅は、資格がなくても設計を行うことができます。
建築に関わる様々な業務をおこなうことはできませんが、一般的なサイズの住宅の設計をするために、不動産会社や工務店には建物の設計のみを担当する設計士が在籍しています。
しかし、建築士のようにマンションやビルなど、大きな建物の設計を行うことはできません。
他にも様々な制限があり、業務として携われる範囲は狭くなっています。
収入の違い
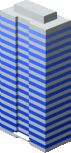
このように両者の間には業務内容にも差があるので、違いは得られる収入にも現れています。
建築士は業務の範囲が広く、国にも認められている資格なので、安定した生活ができるほど平均年収は高めです。
能力によって違いはありますが、平均年収は600万円程度と言われているほどです。
一方の設計士は、業務の範囲が狭く資格も取得していないので、収入は低くなっています。
まとめ
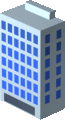
それぞれにはこのような違いがありますが、両者を同じ呼び方で呼ぶことも少なくありません。
特に建築関係に疎い人には、違いがあっても理解できず、同じ人たちだと思うでしょう。
そのため、国家資格のある建築士のことを設計士と思ってしまいますし、反対に国家資格がないのに国によって認められていると思ってしまいます。
ですが、両者は法律によって区別され業務範囲も異なるので、注文住宅の設計を依頼するときには、相手の肩書きには念のため注意しておくと良いでしょう。
卒業生の体験談多数、自分に合った大学選びの参考にしてください。