1級建築士・2級建築士の受験資格。通信制大学・通信講座。
木造建築士の仕事内容

テレビなどで「一級建築士」などの職業を耳にすることが増えてきましたが、実際にどのような仕事をされているか御存知でしょうか。
一言に「建築士」と言っても細かく分類すると山ほどあります。
例えば、木造建築物の設計や工事管理を行う「木造建築士」は国家資格試験に合格し、資格を取得することが必須である職業です。
木造建築士の仕事内容
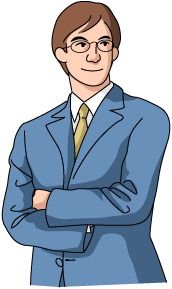
木造の建築物は1階、もしくは2階建ての建物でなおかつ延べ面積が300平方メートル以下の建築物となります。
その用途は住宅をはじめ、公共施設や店舗、賃貸住宅から商業施設まで様々な施設に適応することができます。
その分、多くの知識を必要とされるので試験も学科や設計製図などで優秀な成績を求められます。
多くの方は大学や専門学校で建築科などで学習し、試験に挑みます。
国家資格を取得すると、木造建築物に対する「設計」と「施工」を行えるようになります。
設計では依頼内容の建築物を専門的な知識をもって検証し、計画を立案します。
建物内の電気や排水なども考慮するものであり、どのような建築物になるかはこの設計で決まる重要なものです。
また、計画した建築物の施工にはどのような建築重機や資材が必要なのか、作業員はどの位手配が必要なのか、施工開始から完成までの計画も必要になります。
施工では実際に立案した計画通りに工事を行い、現場で管理を行います。
このように、実際の建築作業以外にも依頼者とのやりとりや現場での作業員に対してもある程度のコミュニケーション能力が求められる職業でもあります。
また、想定外の出来事や万が一の事故に対しても管理者として適切な判断を求められることもあるでしょう。
木造建築士は「一級建築士」や「二級建築士」と比べると対応できる建築物には制限があります。
しかし、「一級建築士」や「二級建築士」は木造建築士からステップアップしてなるものであり、土台である木造建築士での経験は非常に大切なものであると言えるでしょう。
木造建築士の試験はこんな内容です。
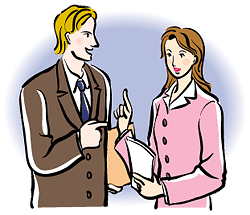
ちなみに、木造建築士の国家試験は毎年7月に学科、10月に設計製図のテストを行います。
受験資格は大学などで建築課程を卒業するか、木造課程を卒業後に実務経験を1年以上積むことなどが求められ、学科では建築に関する知識が求められ、関連の法律も試験範囲となります。
設計製図の試験では事前に発表される課題に取り組むことになります。
建築関係では初歩的な資格ですが合格率は非常に低く、毎年3割程度となっています。
木造建築士試験の受験資格は通信制大学でも取得することができます。
卒業生の体験談多数、自分に合った大学選びの参考にしてください。