1級建築士・2級建築士の受験資格。通信制大学・通信講座。
建築家と建築士の違いは何?
建築士と建築家は同じように見えて全く違う概念です。
混同しやすい建築士と建築家の違いについて説明します。
建築士とは?

一定規模以上の建築物の設計や監理を行うのに必要な、独占的な資格です。
一級は、学校、病院、公民館、劇場、百貨店などの不特定多数が集まる施設で、床面積が500㎡以上の建物の設計を行うことができます。
また、構造が木造の場合は、床面積が1,000㎡以上、かつ、2階建て以上の場合に一級の資格が必要となります。
二級と木造の資格は、主に住宅の設計を行うためのものです。
木造建築士の資格は、一定期間以上、大工の経験のある者でも、学歴に関わらす取得できます。
建築士の関わる仕事としては、建設会社での設計、及び、施工管理の仕事、工務店での現場監督の仕事があります。
設計事務所においては、設計と監理のみを行います。住宅メーカーに所属した場合は、住宅の設計や現場管理を行います。
役所でも活躍の場があり、都市計画や街並みの計画、公共工事の計画や工事管理に携わります。
また、建築物の着工前に必要となる建築確認申請の業務にあたります。
建築家とは?
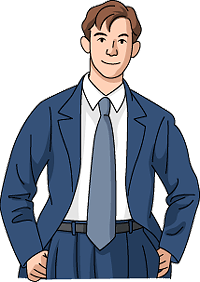
一方、建築家という呼称は法律により定められたものではなく、起源は欧米にあります。
欧米で建築物を建てる場合は、設計と施工は分離されます。同じ組織が設計と施工を同時に担当することは、一般的にはありません。
欧米では建築物の設計は設計事務所に所属する設計士が行います。
この設計士を英語で、アーキテクチャ(architecture)と呼び、日本語で建築家と訳されています。
明治時代以降、日本でも設計を専門に行う設計事務所が設立されました。当初は施工業者から独立し、施主からの依頼を受け、設計業務のみをおこなっていました。
欧米での設計事務所は施工業者からは独立した組織ですが、日本では、建設会社や住宅メーカーも設計事務所を兼ねています。
日本では独立した設計事務所と、施工業者を兼ねる設計事務所との間で決定的な溝があり、お互いにお互いの存在を認めていません。
日本では歴史的に、建築物は大工の棟梁が請け負ってきました。設計と施工は分離されることなく、現代の建設会社や工務店に引き継がれています。
そこに、明治時代以降、欧米の文化に影響を受けた人たちが新たに設立したのが設計事務所です。
日本でも独立した設計事務所で設計を行う設計者を建築家と呼び、現在も変わっていません。
独立した設計者にも役割分担があり、プラン設計と全体のまとめ役である意匠設計者、構造計算を担当する構造設計者、電気設備と機械設備を担当する設備設計者に分かれます。
この中で、建築家と呼ばれるのは意匠設計者だけです。
卒業生の体験談多数、自分に合った大学選びの参考にしてください。